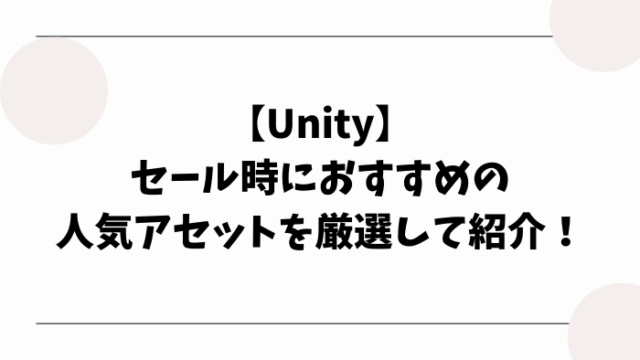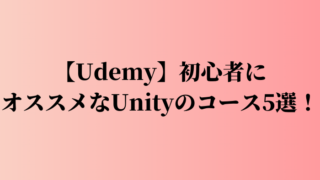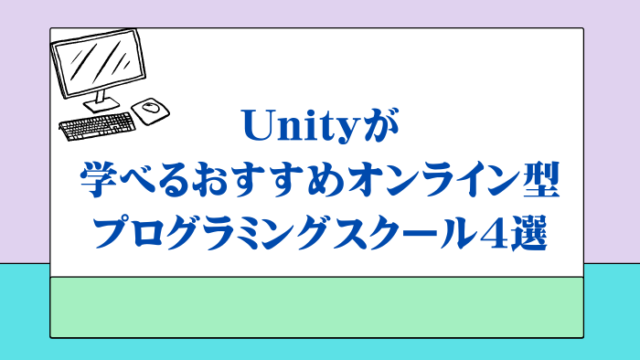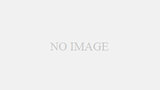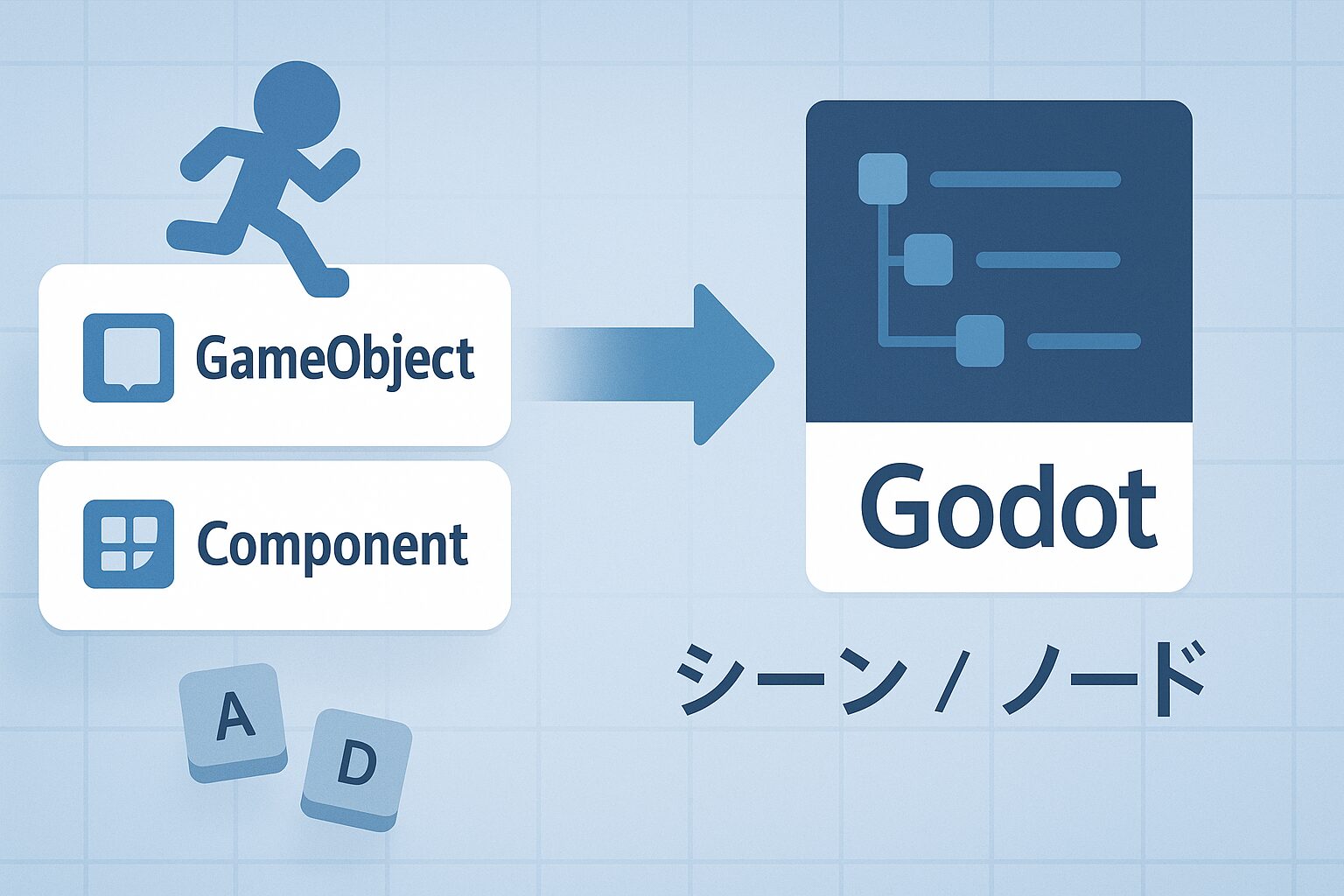今回は、私がサウンドノベルの開発を行っていく中で得られた収穫について記しておこうかなと思います。
Unityでサウンドノベルを開発してみて分かったメリット
なぜUnityなのか
なぜUnityを使用してサウンドノベルの開発を行っているのかという点ですが・・・。
1) マルチプラットフォームを一括で
PC・モバイル(iOS/Android)・WebGLなど主要プラットフォームに同一プロジェクトから書き出しできます。将来的な展開(イベント用のPC版→スマホ版など)にも強いです。
2) 音まわりが強い(サウンドノベルの要)
AudioMixerでBGM/SE/ボイスをグループ管理、フェード・サイドチェイン・状態遷移もGUIで設定可能。ボイスの先読み・遅延再生、シーン跨ぎのBGM持ち越しも簡単です。
3) 手触りを上げる演出ツールが充実
Timelineでキャラ立ち絵の登場、テキスト表示、SE、背景切替をノンリニア編集のように同期できます。Animatorで瞬き・口パク、Cinemachineで2Dカメラワークや被写界深度風の表現も可能です。
4) テキスト表現の自由度
TextMeshProで美しい文字表示、縁取り・グラデ・ふきだし・リッチテキスト装飾に対応。禁則やウェーブ・タイプライタなどテキストアニメも作りやすいです。
5) コードでもノーコードでも進められる
C#で堅牢なテキストエンジンを作るもよし、VisualScriptingで簡易プロトタイプを組むもよし。チームのスキルに合わせて選べます。
6) アセット/拡張エコシステム
UnityのAssetStoreには、サウンドノベル/ADV向けの台詞スクリプト、セーブ、既読・未読、スキップ、選択肢などを一式カバーするフレームワークやUI、効果音、背景素材が多数。必要なところを買い足して制作を短縮できます。
7) スケールに強い設計
ScriptableObjectやAddressablesでシナリオ・ボイス・背景をデータ駆動に管理。章ごとダウンロードコンテンツや差分配信も見据えた構成が取りやすいです。
8) ローカライズ・アクセシビリティ
UnityのLocalizationで多言語切替、右から左(RTL)やフォント切替もOK。ログ機能、オート、早送り、フォントサイズ調整などアクセシビリティ要件を一元的に実装できます。
9) 運用・成長の下支え
Analyticsで読了率や分岐到達率を計測。IAP/広告の導入、限定スチルの期間解放やイベント配信などの運用にも適しています。
10) ノベル+αの拡張余地
ミニゲームや3D背景、Live2D等の表情演出、AR/VRイベントへの発展まで同じ技術スタックで対応可能。IP展開に強いのがUnityの大きな魅力です。
具体的な制作フロー
アセットストアには様々な有能アセット達が多数存在していますが、私はほぼほぼChatGPTと共に開発を行っています。個人開発者の私にとってChatGPTはいわば相棒みたいなものです。
-
シナリオ整備
ChatGPTで台本→ID・分岐・ボイスを付ける。 -
データ設計
台詞・背景・立ち絵・BGM/SEをScriptableObject化。音声はにじボイスを使用しています。 -
入力
ScriptableObjectにてテンプレートが完成したら、後はひたすらセリフの入力やどこで誰が喋るのか背景やボイスを当てはめていく作業です。
超ざっくりですが、入力の前には、シナリオマネージャーなど様々なスクリプトを作る必要があります。マネージャーがScriptableObjectで作った各シナリオデータを管理する仕組みです。
実際に作ってみて分かったメリット
なんだかんだChatGPT凄い
ChatGPTの凄いところは、シナリオだけでなくキャラクターや背景画像も一緒に作ろうと思えば作れてしまうところです。
私のように絵が描くのが苦手な人には凄く重宝します。私は有料プランを使用しているので、画像の生成も大量に行うことが出来ます。
開発の効率を高めたい場合にはProプランぐらいには加入しておくと捗ると思いますよ。
制限に引っかかることもないので、ありとあらゆる背景や喜怒哀楽が伴ったキャラクターの画像を量産することが可能です。
テンプレートまで完成させると楽。(時間はかかるけど)
ひたすらセリフ等の入力処理のみという段階まで進んでくると後はひたすら流れ作業なので、頭を使う作業は少なくなります。
もちろん、スクリプトを組むのが苦手という方はコーディングもChatGPTに頼めば良いと思います。
理想の挙動をしてくれるように、何度も指示を与える必要があると思いますが、繰り返していくうちに思い通りの挙動に近づいていく事だと思います。
どのくらいのシナリオかによって作業時間が変わってくると思いますが、最後にはひたすらシナリオデータの入力が待っているんじゃないかと思います。
テンプレートを1つもっておくだけで、他の作品を作りたいとなった際に「シナリオ」「背景」「キャラクター」「ボイス」を差し替えるだけで他の作品に様変わりするので、色々なサウンドノベルゲームを量産することが出来るようになりますよ。
よくある懸念と対策
-
学習コストが不安
→ 既存のADV/ノベル向けフレームワークやテンプレートを使えば初期実装を短縮できます。小さく作ってから拡張を。 -
ビルドサイズが大きい
→ WebGLやモバイル向けでは、音声の圧縮設定(Vorbis/ADPCMの使い分け)、コードストリッピング、Addressablesによる分割で対処。 -
演出調整に時間がかかる
→ Timelineで可視的に同期、プレハブ化+Prefab Variantsで量産が効く構成にする。 -
分岐デバッグが大変
→ シナリオID単位でジャンプ起動、到達率のAnalytics可視化を仕込むと改善。
Unityが特に向いているケース/そうでないケース
向いている
-
マルチプラットフォーム展開や長期運用を見据える
-
ボイス・BGM演出にこだわりたい
-
ノベル+ミニゲームや3D表現を組み合わせたい
-
将来のIP拡張(イベント、AR/VR)も検討
他エンジンが向く場合も
-
PCのみ・最小構成テキストを出すだけなら、より軽量な専用エンジンも選択肢。
-
チームの経験・予算に応じて必要十分な道具を選ぶのがベストです。
まとめ
サウンドノベルはシンプルに見えて、クオリティは演出と運用で決まるジャンルです。Unityは、音・演出・拡張・配信・運用までワンストップで支えるエコシステムが強みです。
まずはミニマム機能で1章を完成→データ駆動にしてスケール、という進め方が失敗しにくいですよ。