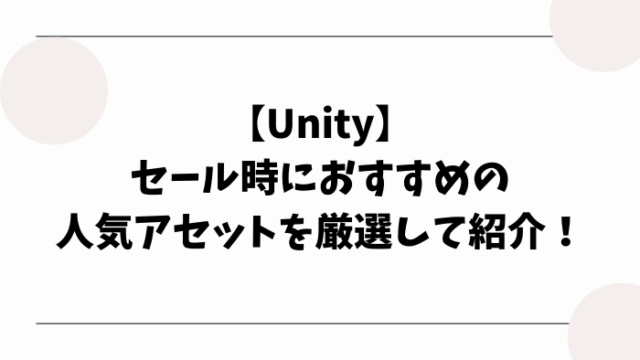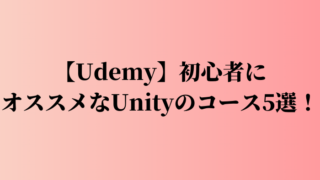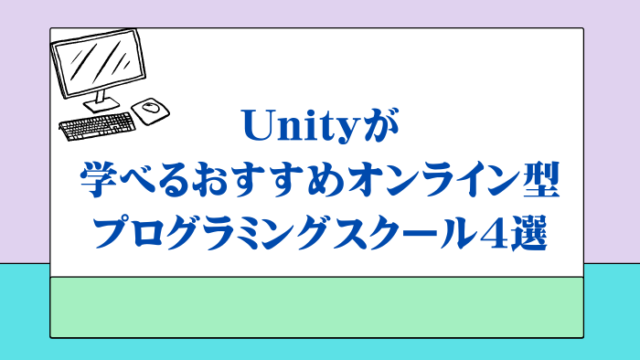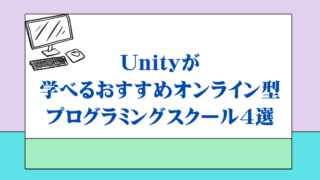「Unityやるぞ」と思っても、実はやりたいことによって学ぶ順番がぜんぜん違うんですよね。
今回は、作りたい目的別に応じたUnity学習のロードマップを紹介したいと思います。
VRがやりたい?スマホゲーム?目的別・Unity学習ロードマップ
-
VRで手を動かしたい人
-
スマホで遊べるカジュアルゲームを出したい人
-
PC向けにちょっとリッチなインディーを作りたい人
-
建築・製造系でリアルタイム3Dを使いたい人
これ、同じ「Unity」でも触る機能・覚える優先順位・詰まりやすい場所がバラバラです。
0. 全ルート共通でやる前準備7日間
ここはみんな一緒です。ここを飛ばすと、あとでバージョン違いやインプットシステムでこけます。
-
Unity Hub + LTS(2022 LTS または現行LTS)を入れる
-
後でVR/モバイル/URPに行きやすい安定版にしておきます。
-
-
プロジェクトは用途別に分ける
-
VRテスト用”モバイル用で分けると設定がごちゃらない。
-
-
Input Systemは新しい方を前提にする
-
これからはほぼこれ。古いInput Managerは「古いアセットのときだけ」。
-
-
GitかPlastic SCMでバージョン管理を作る
-
VRもスマホも、試行錯誤が多いので戻れるように。
-
-
ビルドのゴールを決めておく
-
VR=「手を動かして何かを掴む」
-
スマホ=「1シーンのループが遊べる」
-
PC=「WASDで歩ける+UIが出る」
-
-
ログを残すノートを用意
-
あとで質問するときに強い。
-
-
参考にするUI・映像を3つだけ決めておく
-
ゴールがぼやけるのを防ぎます。
-
ここまでできたら、いよいよ目的別です。
1. VRをやりたい人のロードマップ
VRは「触れる」体験をつくるので、シーンの美しさより手の正しさを先にやります。ここではアセットを選ぶ前の工程をメインにします。
1-1. 1〜30日:操作まわりを固めるフェーズ
-
Unity新規プロジェクト(URPでもOK)をVR向けテンプレで作成
-
コントローラーを表示して「掴む・投げる・押す」の3アクションだけ実装
-
手の高さ・移動速度などを実機で毎回確認(ここをサボると後半つらい)
-
プレハブ化して「掴めるオブジェクト」を量産できるようにする
この段階では見た目を作り込まないほうが学習が速いです。マテリアルは標準でOK。
1-2. 31〜60日:インタラクションを増やすフェーズ
-
ドア・スイッチ・UIのオンオフなど2〜3手順の操作を追加
-
シーンのスケールを現実に合わせる(1mが1mになるように)
-
プレイヤーの酔い対策を実装(テレポート移動かスムーズ歩行かを選ぶ)
-
ここで初めてアセット導入を検討
おすすめのVRアセットは下記にて紹介しています。
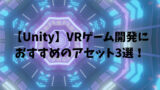
1-3. つまづきやすいところ
-
デバイスごとの設定差(Quest・PCVR)で迷子になる
-
手の当たり判定が大きすぎて誤操作が起きる
-
テストが1人でしかできず、改善サイクルが遅い
1-4. 抜け道
-
早い段階で「操作まわりを見てくれる人」か「VRに詳しい講師」がいたほうが速いです。ここは独学で引っ張るより、短期で聞けるオンライン講座に1回だけでも投げるほうがコスパいいです。
→ 比較はこちらにまとまっています。
2. スマホゲーム(Android/iOS)を出したい人のロードマップ
モバイルは、最初から軽く作る意識があると後がラクです。ここでは「企画を小さくしてビルドまで行く」ことを主眼にします。
2-1. 1〜30日:1画面で完結するゲームを作る
-
例:タップでジャンプするだけ / スワイプで避けるだけ
-
解像度を最初に決める(1080×1920想定など)
-
UIはCanvas 1枚+ボタン2つに制限
-
実機ビルドを1週目にやる(「最後にやる」はNG)
ここで「ビルドまで行く経験」をしておくと、以後の学習が全部スマホ前提で進められます。
2-2. 31〜60日:運営に必要な地味スキルを足す
-
スコア保存(PlayerPrefsでOK)
-
タイトル→ゲーム→リザルトの3シーン遷移
-
シンプルな広告挿入・アナリティクス設置の勉強
-
同じゲームをスキン違いで2本目を作る(使い回しを学ぶ)
2-3. つまづきやすいところ
-
画面サイズが端末によって崩れる
-
広告・課金系のSDKでつまずく
-
もっと凝った演出をと寄り道してリリースが伸びる
2-4. 抜け道
-
先に「1画面完結テンプレ」を自作しておき、今後のゲームは全部そこからスタート
-
レイアウトはSafeArea対応のプレハブを1つ持っておく
-
SDKで詰まったら、実装だけスポットで聞ける環境に投げる
3. PC向け・インディー寄りに行きたい人のロードマップ
ここは「長く作る」人向けです。ここでは長期開発を破綻させないための学習順序についてまとめておきます。
3-1. 1〜30日:操作とカメラを固定する
-
TPSまたはFPSのどちらかに決める(両方やると迷走)
-
カメラワークをCinemachineで統一しておく
-
プレイヤーの状態と見た目を分ける(前に書いた記事とも繋がるポイント)
-
PC向けの入力(キーボード+マウス)をテストシーンで確認
3-2. 31〜90日:システムを分けて育てる
-
戦闘/インベントリ/セーブ/クエストのようにサブシステムごとに小プロジェクトで検証
-
OKなら本番プロジェクトに輸入する(失敗したら捨てる)
-
レベルデザインは別シーンで作って、最後に統合
-
URPの最適化やポストプロセスはこの段階で
3-3. つまづきやすいところ
-
シーンが大きくなりすぎてロードに時間がかかる
-
フォルダ構成がぐちゃっとしてどこに何があるか分からない
-
長い開発でモチベが落ちる
3-4. 抜け道
-
月1回、誰かに見せる日を作っておく(スクール・コミュニティ・XでもOK)
-
大型機能は検証プロジェクト→本体に移植の2段階にする
-
レビューしてもらえるところにだけ時々お金を使う
4. 建築・製造・業務でUnityを使いたい人のロードマップ
4-1. 1〜30日:データを持ってくるところまで
-
CAD/BIMやDCCツールからのFBX/GLTFインポートのやり方を覚える
-
マテリアルをUnity側で差し替えて、最低限見られる状態にする
-
カメラのパスやウォークスルーを設定して「見せる」段階にする
4-2. 31〜60日:操作&UIを整える
-
マウス操作でのビュー移動・オブジェクト選択・情報表示
-
ヒエラルキーに沿ってオブジェクトを検索して表示するUI
-
モバイルやWebGLにも持っていけるかの確認
4-3. つまづきやすいところ
-
元データが重くてUnityで軽く動かない
-
誰に見せるかでUIの作りが変わる
-
Webに出すときの制約が大きい
4-4. 抜け道
-
最初から軽量化・最適化が分かる人に一度聞く(スポットでもOK)
-
Webに出すと決めたら、早めにWebGLでの制限一覧をチェックしておく
-
ここも学習サポートのある講座を選ぶと時短になります
5. どのルートでも共通の「スイッチング目安」
「独学でまだいけるか」「もう外部に頼るか」の目安はシンプルでOKです。
-
同じ問題を3日以上回してる
-
目的が作品づくりから教材消化にずれてきた
-
他人に見せる予定がないまま1か月経った
どれかに当てはまったら、いまのルートを一度比較してもらえる場所に持っていくタイミングです。
この記事のまとめ
-
学ぶ順番は目的で変わります。
VR・スマホ・PCインディー・業務活用(建築/製造)で、優先すべき機能と詰まりやすい場所が違います。 -
全員共通の前準備(7日)
LTSで環境統一 → 用途別プロジェクト分割 → 新Input System前提 → 版管理(Git/Plastic) → 小さなビルド目標の設定 → 学習ノート → 参考UI/映像を3つ固定、の順で土台を作ります。 -
VRルートの核心
まずは「掴む・投げる・押す」の操作を正しく。見た目は後回しでOKです。早期に実機検証と酔い対策を回すと後半が楽になります。 -
スマホゲーム(Android/iOS)ルートの核心
1画面で完結する小さなゲームを先に出します。解像度固定・実機ビルド先行・UI最小構成がポイントです。運営に必要な保存/遷移/広告は2か月目から。 -
PCインディー(リッチ)ルートの核心
操作+カメラ(Cinemachine)を先に固定し、戦闘やクエストなどは小プロジェクトで検証→本体へ移植の2段構えにします。長期化を破綻させない設計が最優先です。 -
建築/製造など業務活用ルートの核心
まずはデータの持ち込み(FBX/GLTF)→最低限の見映え。次に選択・表示UIやウォークスルーを整え、WebGL/モバイルの制約は早めに確認します。 -
よくある詰まりと共通の抜け道
同じ問題を回り続ける、SDKやデバイス差で迷子、長期開発で迷走…といった壁は、
①最小再現で切り出す → ②質問テンプレで聞く → ③レビューを定期化、の三段ルーチンで抜けやすくなります。 -
スイッチング(外部活用)目安
-
同じ問題を3日以上回している
-
目的が作品づくり→教材消化にズレた
-
他人に見せる予定が1か月ない
いずれかに当てはまったら、スポットでメンター/講座を使うと効率が上がります。
-